この記事は 2025年8月29日 に更新されました。
脚本を書くときに「ト書きってどう書けばいいの?」と悩む人は多いです。
小説の地の文とどう違うのか、心理描写はどう表現すべきか、初心者にとってはわかりにくい部分でもあります。
この記事では、ト書きの定義と役割、書き方のコツ4つ、例文やNG例 を紹介します。
具体的な例を通して理解できるので、脚本コンクール応募やシナリオ作成にも役立ちます。
初めて脚本を書く方も、すでに執筆経験のある方も、「映像化できる文章」としてのト書き を学び直すきっかけにしてください。
目次
ト書きとは?脚本における役割と由来

ト書きの定義(脚本の三要素のひとつ)
脚本は 柱書き・セリフ・ト書き の三要素で構成されています。
このうちト書きは、登場人物の動きや場面の状況を説明する部分です。
たとえば「葬儀会場から参列者が出てくる」「雨が降り始める」といったように、観客が映像として目にできる事柄だけを書く のが基本です。
由来:「セリフのあとに“ト”と書いたことから」
「ト書き」という言葉の由来は、日本の伝統演劇にあります。
歌舞伎ではセリフのあとに「ト回る」「ト立つ」といった動きを必ず書いており、そこから “ト書き” という名称が生まれました。
現代の脚本でも同様に、セリフ以外の動きや状況を伝える部分を「ト書き」と呼びます。
脚本での重要性(製作者に意図を伝える役割)
ト書きは小説の「地の文」と混同されやすいですが、役割は大きく異なります。
- 小説の地の文 → 一般読者を楽しませるための文章。情緒的で間接的な表現も多い。
- 脚本のト書き → 監督・俳優・カメラマンなど制作スタッフに意図を正しく伝えるための文章。簡潔で明快でなければならない。
もしト書きがあいまいだと、演出や演技が脚本家の意図からずれてしまいます。
そのため、ト書きは脚本の中で「制作現場と脚本家をつなぐ設計図」として非常に重要な役割を担っているのです。
補足:小説とト書きの違いを例文で比較
太宰治『グッド・バイ』の冒頭は次のように始まります。
文壇の、或る老大家が亡くなって、その告別式の終り頃から、雨が降りはじめた。早春の雨である。
太宰治『グッド・バイ』
これは文学的で情緒的な描写です。
一方、これをト書きに直すと次のようになります。
葬儀会場から参列者が出てくる。
雨が降り始め、梅を濡らす。このように、小説の表現を映像化できる形に落とし込むのがト書き です。
ここでは「早春」を直接書かず、「梅を濡らす」という映像で表現しています。
ト書きの書き方コツ① 箇条書きで明確に伝える

曖昧な文章が生む誤解(NG例)
ト書きは製作者に誤解なく伝えることが最も大切です。
ところが、修飾語が多すぎたり、文章が一文で長すぎると、意図が正しく伝わらなくなります。
例:
大きくて傷がついたポストの前に停まる車→ 「大きくて傷がついた」のが ポスト なのか 車 なのか不明。
英子は涙を流して泣く美衣子の頭をなでる→ 泣いているのは英子か美衣子か、どちらかわからない。
このような曖昧な文章は、現場の解釈を迷わせてしまいます。
箇条書きで改善した例文
曖昧さをなくすためには、一文で詰め込みすぎず、箇条書きに分けるのがおすすめです。
例:
傷のついたポスト。
その前に大きな車が停まる。
涙を流している英子。
同じように泣いている美衣子の頭をなでる。このように書くことで、状況と行動が明確に分かれ、誰が何をしているか がひと目でわかります。
修飾語を整理するコツ
ト書きを書くときは、修飾語の使い方に注意が必要です。
修飾語は一つの対象にだけかかるようにすることで、意味の取り違えを防げます。
また、一文に情報を詰め込みすぎず、「AはBするC」といった形ではなく、
「A。BするC。」のように 文を分けて書く のが効果的です。
さらに、登場人物と行動を切り分けて書くことも大切です。
たとえば「田中、歩いてくる」と書けば、
「登場人物=田中」「行動=歩いてくる」と役割が明確になり、読み手にとって理解しやすくなります。
ト書きの書き方コツ② 心理描写は映像で表現する

心情を直接書くのはNG例
ト書きでは「登場人物の気持ち」をそのまま文字で書くことはできません。
たとえば次のような書き方はNGです。
太郎は動揺しているこれでは「動揺している」という情報しかなく、カメラにどう映すか が不明確です。
制作スタッフは「顔を青ざめさせる?」「声を震わせる?」と迷ってしまいます。
行動で心情を示す改善例
心理描写は、行動や状況を通して観客に伝える のが鉄則です。
NG例を改善すると、次のようになります。
太郎、水差しからコップに水を注ぐ。
手が震えてこぼしてしまう。「手が震えて水をこぼす」という動作を入れることで、太郎が動揺していることが自然に伝わります。
セリフやナレーションに頼らなくても、映像だけで心情を表現できるのです。
観客に伝わる心理描写のコツ
- 日常的な行動を失敗させる → 不安・動揺を表現しやすい
- 表情や仕草を描く → 喜怒哀楽をシンプルに伝えられる
- 小道具を使う → コップ・ペン・携帯電話など身近な物が効果的
このように「映像で伝えられる心理描写」を意識すれば、観客も制作スタッフも迷わずに理解できるト書きになります。
ト書きの書き方コツ③ 不要な部分をカットして簡潔に

冗長なト書きの例
初心者が書いたト書きに多いのが、細部をすべて描写してしまうケースです。
たとえば次のような例です。
休み時間の教室。
窓際の席では数人の女子がおしゃべりを楽しんでいる。
黒板に書かれた前の授業の板書を消している日直。
二つの机をくっつけてスマホゲームをしている数人の男子。
自席で早弁をしているふくよかな男子生徒。
遅刻して入ってくる佐藤。これでは“休み時間の様子”は伝わりますが、冗長で読みにくく、主題がぼやけてしまいます。
主役の行動だけに絞った改善例
もしこのシーンで伝えたいのが「佐藤が遅刻してくる」ことだけなら、余計な描写は削るべきです。
改善例:
休み時間。騒がしい教室。
遅刻してくる佐藤。これだけで「教室の雰囲気」と「佐藤の行動」が明確に伝わり、余計な情報に邪魔されません。
「スポットライトを当てる」意識
ト書きでは「一行ごとに何を伝えたいのか」を意識してください。
- 主人公の行動を目立たせたいなら、余計な背景描写は削る
- 背景や雰囲気を見せたい場合も、短い言葉でまとめる
たとえ一行のト書きでも、存在する意味を考えることが大切です。
不要な部分をカットすることで、脚本全体のテンポも良くなり、読みやすい文章になります。
ト書きの書き方コツ④ 映像をイメージしてリアリティを出す

曖昧な設定がNGな理由
ト書きには何でも書ける自由がありますが、だからこそリアリティの欠如が問題になります。
たとえば次のような書き方は、漠然としていて映像化が難しいです。
宇宙人が降り立ったこれでは登場の仕方や状況が曖昧で、監督やスタッフが具体的にイメージできません。
結果として、脚本家の意図と異なる映像になる危険があります。
脳内で映像化できるかをチェック
良いト書きの基準は「脚本家の頭の中で、シーンが映像として再生できるか」です。
映像化できない表現は、読み手にも伝わりません。
改善例:
夜の闇。
林の奥が発光している。
木々を掻き分けるように、銀色のヒトガタ生命体が現れる。ここでは「夜」「林」「発光」「銀色のヒトガタ」という具体的な要素で、映像が目に浮かぶようになっています。
リアリティを高める取材の重要性
映像をイメージする力を養うには、取材や観察が役立ちます。
- 実際の場所に足を運んでみる
- 写真や映像資料を確認する
- 日常生活の動作や会話を観察する
リアリティは「想像」だけでなく「実体験」からも生まれます。
こうして積み上げたディテールが、観客に説得力を持つ脚本につながります。
まとめ|脚本のト書きは「映像化できる文章」が基本
ト書きは脚本の中では地味に見えますが、制作現場に意図を正しく伝える要の部分です。
一行ごとの描写が映像化できるかどうかが、脚本全体の完成度を大きく左右します。
今回紹介した4つのコツを振り返りましょう。
✅ ト書きの4つのコツ
- 箇条書きで書く → 誤解のない明確な表現になる
- 心理描写は映像で表現する → 行動で心情を伝える
- 不要な部分をカット → 主役の行動を際立たせる
- 映像をイメージして書く → 読み手にリアリティが伝わる
これらを守れば、脚本コンクール応募にも通用する「映像化できる脚本」が仕上がります。
関連記事でさらに理解を深める
👉 併せて読むことで「脚本の三要素(柱書き・セリフ・ト書き)」を総合的に理解できます。
学習をさらに進めたい方へ
- 📘 おすすめ書籍:
シナリオ教本の古典とも言える本。基礎を抑えられる。
 |
新品価格 |
シナリオ制作のロードマップを理解できる本です。Audibleでは耳で聞くこともできるので、読書が苦手な人におすすめ。
 |
シナリオ・センター式 物語のつくり方 プロ作家・脚本家たちが使っている 新品価格 |
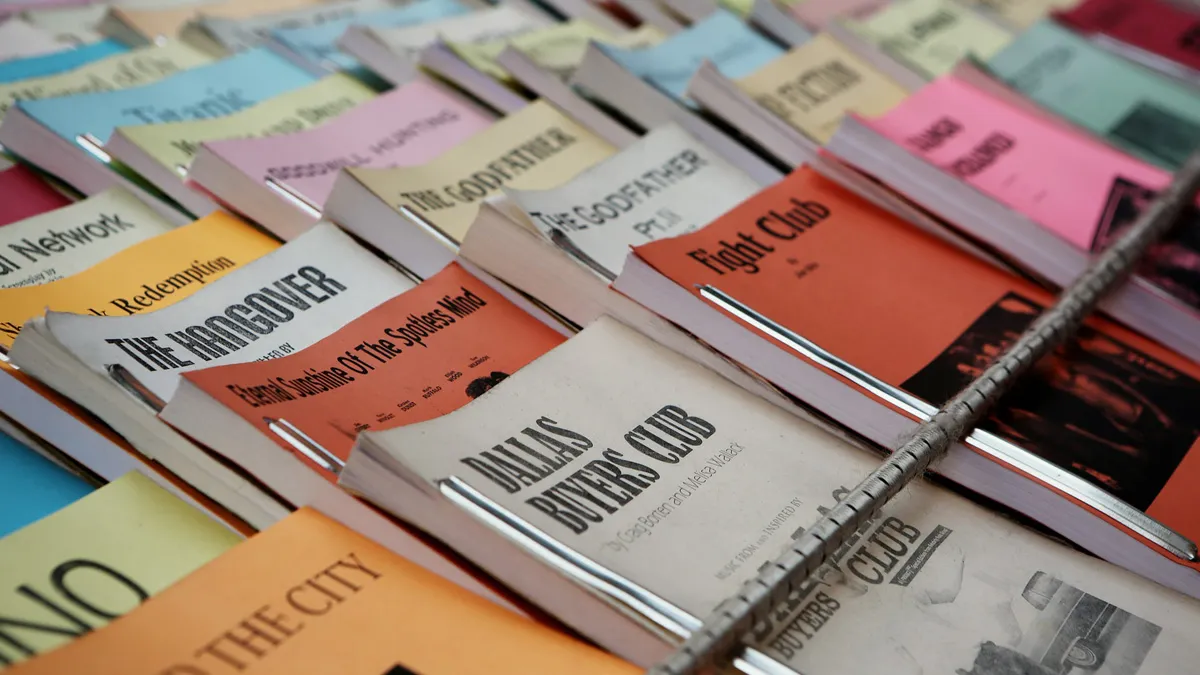

コメント