この記事は 2025年10月10日 に更新されました。
キャラクターは、物語の心臓です。
構成が整っても、セリフが巧くても、登場人物が“生きて”いなければ作品は動きません。
この記事では、名前・外見・人間関係・野心まで、人物を立体化するための22の質問を用意しました。脚本はもちろん、小説や漫画にもそのまま使えます。
作り方のコツは、まずは全項目をざっと埋める(完璧を目指さない)ことです。
後半では、コピペして使える設定テンプレートも掲載します。
それでは、あなたのキャラクターに息を吹き込みましょう。
目次
- 1 🧩 01|名前 ― 印象と物語を決める最初の一歩
- 2 🧩 02|年齢 ― 人生観と行動を決める軸
- 3 🧩 03|外見的特徴 ― 一瞬で“誰か”とわかるシルエット
- 4 🧩 04|出身地 ― 世界観と価値観を形づくる“土のにおい”
- 5 🧩 05|住んでいる場所 ― その人の“現在”を語る舞台装置
- 6 🧩 06|家族構成 ― 性格を形づくる“最初の人間関係”
- 7 🧩 07|友達との関係 ― “社会の中の自分”を映す鏡
- 8 🧩 08|その他の重要な人間関係 ― 影響を与えた“もう一人の他者”
- 9 🧩 09|異性との関係 ― “心の奥”を映す関係性の鏡
- 10 🧩 10|仕事 ― 生き方と価値観を映す“日常の顔”
- 11 🧩 11|服装(ファッション) ― “見た目”に宿る内面のサイン
- 12 🧩 12|趣味 ― “本当の自分”が顔を出す時間
- 13 🧩 13|最高の長所 ― “光”の部分をどう輝かせるか
- 14 🧩 14|最低の短所 ― “人間らしさ”を生む影の部分
- 15 🧩 15|思考の柔軟性 ― “変化を受け入れる力”がドラマを生む
- 16 🧩 16|性格 ― 行動の“原動力”を一言で表す
- 17 🧩 17|他人との関わり方 ― “距離の取り方”が人間性を語る
- 18 🧩 18|他者からの印象 ― “見られ方”が生むギャップのドラマ
- 19 🧩 19|脚本の途中で芽生える特徴 ― “変化”こそキャラクターの生命線
- 20 🧩 20|野心(目標) ― 物語を動かす“エンジン”
- 21 🧩 21|そのキャラクターの重要ポイント ― “一言で語れる人物像”をつくる
- 22 🧩 22|敵か味方か ― “立場”がキャラクターを際立たせる
- 23 🧒 子供キャラクター設定の作り方 ― “未完成さ”をどう描くか
- 24 🧭 まとめ ― キャラクターは“設定”ではなく“呼吸する存在”
- 25 📥 テンプレート配布
🧩 01|名前 ― 印象と物語を決める最初の一歩
Q:その名前を聞いた瞬間、どんな人物を思い浮かべてほしいですか?
名前は、キャラクターの「最初のセリフ」です。
言葉を発しなくても、名前の響きだけで性格や雰囲気を感じ取らせる力があります。
たとえば「桐生」「一ノ瀬」なら硬質でクール、「ひなた」「夢」なら柔らかく温かい印象を与えるでしょう。
ただ、意味づけを詰め込みすぎると不自然になります。
理屈よりも直感とリズムを信じてください。実際に口に出して、耳で確かめるのがいちばんです。
映像化を意識する脚本なら、発音しやすさ・聞き取りやすさも重要です。
観客が混乱しない名前――それだけで印象が残ります。
💡 ポイント
- 呼び名やあだ名も先に決めておくと会話が自然になる
- 物語のトーン(和風/洋風/現代/ファンタジー)に合わせる
- 他キャラと語感を差別化する
🧩 02|年齢 ― 人生観と行動を決める軸
Q:そのキャラクターは、どんな時代の空気を吸ってきた人ですか?
年齢は、外見の数字ではなく「思考の背景」を示します。
10代なら衝動で動き、20代なら理想と現実の間で揺れ、30代なら覚悟と諦めを行き来する──
同じ行動でも、年齢によって意味が変わります。
たとえば「走る」という動作。
17歳なら逃げるため、27歳なら追うため、37歳なら守るためかもしれません。
年齢は物語の温度を変える要素なのです。
ざっくり年代で済ませず、ジャストの年齢を決めましょう。
「29歳」と「30歳」では、置かれている心境が違います。
また、過去の年齢(中学時代/20歳の頃)を一行メモしておくと、キャラの成長や変化も描きやすくなります。
💡 ポイント
- 数字に意味をもたせる(「29歳=ギリギリの焦り」など)
- 年齢と話し方・語彙のバランスを取る
- フラッシュバックや回想で“年齢差”を活かすと物語が立体化する
🧩 03|外見的特徴 ― 一瞬で“誰か”とわかるシルエット
Q:その人物を後ろ姿だけで見分けられますか?
外見は、キャラクターの第一印象を決める「視覚のセリフ」です。
長身・小柄・猫背・笑いじわ──たった一つの特徴で、観客や読者の記憶に残ります。
派手な装飾や奇抜な髪色よりも、「その人らしい自然な違和感」が鍵になります。
たとえば、いつも髪を結ぶ位置が少しだけずれている。
寒い日でも半袖を着ている。
話すたびに手をいじる癖がある。
そんな細部は、セリフより雄弁にキャラクターを語ります。
大きな傷跡や義手といった象徴的な要素を与えるなら、
それが“なぜそうなったか”という物語の根も一緒に考えてください。
外見にストーリーが宿れば、観客は自然と興味を持ちます。
💡 ポイント
- 「他の誰かと間違えない一要素」を決める
- 癖・動き・姿勢も“外見”の一部として設定する
- 外見の変化(髪を切る・痩せる)で心情を示すと効果的
🧩 04|出身地 ― 世界観と価値観を形づくる“土のにおい”
Q:その人は、どんな景色の中で育ったのでしょうか?
出身地は、キャラクターの価値観の“土台”です。
どんな土地で、どんな空気を吸って育ったか。
それだけで、その人の言葉づかいや考え方、歩き方まで変わってきます。
たとえば、海辺で育った人は潮風に強く、どこかおおらか。
山に囲まれた地域なら慎重で粘り強い。
都会育ちならスピード感があり、田舎育ちなら人との距離を近く感じる──。
出身地を設定することは、キャラクターの「地層」を決めることなのです。
物語の舞台と同じでも、異なっていても構いません。
むしろ、舞台と出身地のギャップがあるほうがドラマが生まれます。
東京に出てきた地方出身者、戦地から帰った兵士、海外に渡った留学生──
どこから来たかが、今どう生きるかを語ります。
💡 ポイント
- 風土(気候・方言・食文化)を一つだけ具体化する
- 物語の舞台との距離感を考える(移住・帰省・逃避など)
- 出身地の価値観を裏切る行動をさせると印象的になる
🧩 05|住んでいる場所 ― その人の“現在”を語る舞台装置
Q:いま、そのキャラクターはどんな部屋で眠り、どんな道を歩いていますか?
住んでいる場所は、キャラクターの「今」を映す鏡です。
高層マンションか、古びたアパートか。
シェアハウスか、郊外の一軒家か。
その環境が、性格や行動パターンにまで影響します。
たとえば、狭いワンルームに住む主人公なら、
“閉塞感”や“孤独”が自然とにじみます。
一方、山奥の家に一人で暮らしているなら、
“静けさ”や“こだわり”を表すことができます。
部屋の散らかり具合、窓から見える風景、通勤・通学のルート。
そうした細部を一つでも設定しておくと、
セリフや行動にリアリティが宿ります。
また、住む場所の変化(引っ越し・転居・一時避難など)は、
物語の転機を示すサインにもなります。
場所が変わると、キャラクターの呼吸も変わるのです。
💡 ポイント
- 「部屋の一角」を具体的に描けるか(本棚・ポスター・カーテン色など)
- 住環境が性格をどう映すかを意識する
- 引っ越しや居場所の変化を物語の節目として使う
🧩 06|家族構成 ― 性格を形づくる“最初の人間関係”
Q:その人は、どんな空気の中で育ちましたか?
家族は、キャラクターの「人格の原型」です。
厳格な父に育てられたか、優しい母のもとで育ったか、
あるいは、家族を持たずに大人になったか。
幼少期の家庭環境は、価値観や対人距離に深く影響します。
たとえば、兄弟が多い人は競争心や協調性を持ち、
一人っ子なら自己完結型でマイペース。
祖父母と暮らしていた人は、世代を超えた視点や言葉遣いを自然に身につけます。
「どんな家庭で育ったか」を掘り下げるだけで、キャラクターの今の反応に説得力が生まれます。
家族関係は、温かさだけでなく傷の象徴にもなります。
疎遠な親、亡くした家族、秘密にしている血縁。
そうした背景が、物語の動機や葛藤を支えることもあります。
キャラの現在の行動の裏には、いつも家庭で得られなかった何かがあるかもしれません。
💡 ポイント
- 家族の中での立ち位置(長男・末っ子・養子など)を決める
- 家族との関係性を「一言」で言い表してみる(例:尊敬/反発/依存)
- 家族とのエピソードが行動の理由に繋がるように設計する
🧩 07|友達との関係 ― “社会の中の自分”を映す鏡
Q:その人は、誰と一緒に笑い、誰の前では沈黙しますか?
友達との関係は、キャラクターの「社会的な顔」を表します。
家族が原点なら、友人は現在を示す存在です。
どんな相手と付き合っているかで、性格の輪郭がくっきり浮かびます。
たとえば──
いつも自分を引っ張ってくれる親友がいる人は、依存と信頼の狭間に揺れます。
グループの中で浮きがちな人は、孤独を抱えつつも観察眼が鋭くなるでしょう。
社交的なタイプでも、実は心を開く相手は一人しかいない。
そんな人との距離の取り方が、物語を深くします。
また、友人関係は時間とともに変化します。
幼なじみから敵になる、ライバルが相棒になる──その変化がドラマの燃料です。
どんな関係を築き、どんな関係を失ったのか。
その軌跡こそが、キャラクターの心の地図になります。
💡 ポイント
- 友人関係のバランス(支配する側/される側)を決める
- 「過去の友人」「現在の友人」を分けて考える
- 友情の終わり方を設定すると、キャラの深みが増す
🧩 08|その他の重要な人間関係 ― 影響を与えた“もう一人の他者”
Q:その人の人生を、静かに変えた誰かがいますか?
人は家族と友人だけで形づくられるわけではありません。
人生の節目には、心を動かす他者が必ず現れます。
それは先生かもしれないし、上司、先輩、あるいは敵だった人かもしれません。
たとえば──
落ちこぼれだった生徒に手を差し伸べた教師。
怒鳴るばかりの上司から、仕事の誇りを学んだ部下。
あるいは、たった一言で人生を狂わせた他人の噂。
「関わりの深さ」よりも、「影響の強さ」を基準に思い出してください。
重要なのは、その関係が今のキャラクターに何を残したかです。
信頼か、反発か、恐怖か。
その感情の余韻が、キャラの行動を静かに導いていきます。
💡 ポイント
- 家族・友人以外で「人生の方向を変えた人物」を一人書き出す
- 尊敬・憎悪・恩義など、感情のベクトルを決める
- 敵対者や恩師など、関係性を正反対の存在として描くと印象的
🧩 09|異性との関係 ― “心の奥”を映す関係性の鏡
Q:この人は、誰を愛し、誰に傷つけられたでしょうか?
異性との関係は、キャラクターの感情の深度を測るバロメーターです。
愛され方、愛し方、そして失い方――そのすべてが人間の本質をあらわします。
たとえば、誰にも恋をしたことがない人物は、未知の感情にどう反応するか。
一度だけ深く愛した経験がある人物は、次の恋にどんな恐れを抱くか。
恋愛経験の量ではなく、どんな感情を残してきたかが重要です。
異性との関係を設定するときは、「恋愛の有無」よりも
「関わり方の距離」を意識してみてください。
心の壁を築くのか、無防備に飛び込むのか。
どちらの選択にも、その人の過去と性格がにじみます。
そして、恋愛関係に限らず、異性との緊張感を描くことも効果的です。
憧れ、嫉妬、警戒、支配――それらは愛よりも強い動機になることがあります。
物語に深みを出すのは、愛そのものではなく、愛の扱い方です。
💡 ポイント
- 初恋・失恋・別れなど、記憶に残る出来事を一つ決める
- 恋愛を通じて「何を学んだか」「何を失ったか」を書く
- 恋愛感情以外の異性関係(師弟・敵対・依存)も検討してみる
🧩 10|仕事 ― 生き方と価値観を映す“日常の顔”
Q:その人は、何のために働いていますか?
仕事は、キャラクターの社会での立ち位置を決める要素です。
どんな職業を選び、どんな気持ちでそれを続けているのか。
その答えの中に、人生観や倫理観が自然とにじみ出ます。
たとえば──
医師は命の重さを知りすぎているかもしれない。
警察官は正義と現実の狭間で揺れているかもしれない。
売れない芸人は笑いの裏で、焦りや劣等感を抱えているかもしれない。
仕事そのものよりも、その職業に対する姿勢を設定することが大切です。
「好きだから続けている」のか、「やめられない事情がある」のか。
同じ仕事でも、その理由によってキャラクターはまったく違う人物になります。
また、仕事は物語を動かす装置にもなります。
同僚・上司・取引先など、関係性の幅を広げやすく、
葛藤や選択を生むきっかけにもなります。
どんな作品でも、キャラの仕事=世界観の縮図と考えると良いでしょう。
💡 ポイント
- 職業を選んだ理由を一行で書く(夢/義務/偶然/逃避)
- 「仕事が好きか嫌いか」を明確にする
- 職業を通じて他者とどう関わっているかを考える
🧩 11|服装(ファッション) ― “見た目”に宿る内面のサイン
Q:その人の服装には、どんな性格がにじんでいますか?
服装は、言葉よりも雄弁にキャラクターの心を語ります。
他人の目を意識するタイプか、自分の快適さを優先するタイプか。
服選びの基準ひとつで、その人の価値観が浮かび上がります。
たとえば──
流行を追う人は「他者との調和」を大切にし、
同じ服を何年も着る人は「変化を恐れない頑固さ」や「執着心」を持っているかもしれません。
休日の服装が仕事着とまるで違うなら、それはもう一人の自分の表れです。
服の色、靴の汚れ、アクセサリーの有無――。
ほんの小さなディテールにも、キャラクターの物語が潜んでいます。
また、服装の変化は内面の変化を示す強力な演出にもなります。
恋をした後にメイクが変わる、決意の朝にスーツを着直す、
そうした一瞬に、成長や覚悟を込めることができます。
💡 ポイント
- 「色・質感・清潔感」から性格を推測してみる
- 服装の変化で心情を示す(転職・別れ・喪失など)
- 似合わない服を着ている理由を考えると深みが出る
🧩 12|趣味 ― “本当の自分”が顔を出す時間
Q:その人は、ひとりのとき何をしているでしょうか?
趣味は、キャラクターの「素の部分」を映します。
仕事や肩書きを離れたときに何をしているか――それが、その人の本質です。
たとえば、無口な警官が休日に植物を育てていたら?
強気な上司がこっそり猫カフェに通っていたら?
意外性のある趣味は、キャラクターに温度と奥行きを与えます。
また、趣味は人間関係をつなぐ糸にもなります。
同じ趣味で仲間ができたり、正反対の趣味で衝突したり。
行動のきっかけや出会いの装置として使うと、物語が自然に広がります。
さらに、「人に言えない趣味」も強力な設定です。
隠すことで秘密が生まれ、秘密があることで共感や興味が生まれます。
読者がその秘密を共有していると感じた瞬間、キャラクターは一気に近くなります。
💡 ポイント
- 「なぜその趣味を好きになったのか」を一行で書く
- 趣味を通じて他者とどう関わるかを考える
- 秘密の趣味をひとつ設定すると、物語に陰影が出る
🧩 13|最高の長所 ― “光”の部分をどう輝かせるか
Q:この人の、いちばん誇れるところは何ですか?
長所は、キャラクターを魅力的にする光の核です。
ただし、単に「優しい」「努力家」といった言葉で片づけると、印象が薄れます。
その性質がどんな場面で発揮されるかを想像することで、
長所が生きている力に変わります。
たとえば──
「人を信じる力」がある人は、裏切られてもなお誰かを信じようとする。
「責任感が強い人」は、休むことさえ自分に許せない。
「情に厚い人」は、敵にさえ手を差し伸べてしまう。
長所は行動の原動力であり、同時にドラマを動かすトリガーにもなります。
重要なのは、長所を他人の目線から描くこと。
本人が気づいていない強さを、周囲の人が見ている――
そんな構図にすると、読者もキャラクターを好きになりやすいのです。
💡 ポイント
- 「長所が発揮される瞬間」を具体的に設定する
- 他人から見た長所と本人の自覚を分けて考える
- 長所が物語の光を作り、後の短所と対比されるように配置する
🧩 14|最低の短所 ― “人間らしさ”を生む影の部分
Q:この人が一番嫌われる理由は、なんでしょう?
短所は、キャラクターに血を通わせる「影」です。
完璧な人物よりも、どこか欠けた人物のほうが、読者の心に残ります。
怒りっぽい、臆病、頑固、自己中心的――
そうした欠点があるからこそ、物語の中で成長や葛藤が生まれるのです。
たとえば、優しすぎる人は決断が遅れ、
正義感が強すぎる人は他人を責めてしまう。
短所は、長所と表裏一体であることを忘れないでください。
最低な一面ほど、その人の本音を映します。
また、短所は物語の中で露出するタイミングが重要です。
冒頭で見せれば親近感が生まれ、終盤で見せれば共感が深まります。
読者は欠点のない人よりも、「それでも前に進もうとする人」を応援するのです。
💡 ポイント
- 長所の裏返しとして短所を設定する(例:優しさ⇔優柔不断)
- 短所を失敗エピソードとして一行で書く
- 短所を克服するか、受け入れるかでキャラの成長が決まる
🧩 15|思考の柔軟性 ― “変化を受け入れる力”がドラマを生む
Q:この人は、世界がひっくり返ったとき、どう反応しますか?
思考の柔軟性は、キャラクターの進化の余地を決めます。
予想外の出来事に直面したとき――
現実を拒むのか、受け入れて考え直すのか。
その一瞬の反応に、人間性があらわれます。
たとえば、信じていた友に裏切られたとき。
怒りに支配される人もいれば、自分を見つめ直す人もいる。
同じ状況でも、心の柔らかさによって物語の方向は大きく変わります。
柔軟な思考を持つキャラは、ストーリーを推進させ、
頑ななキャラは、ストーリーに壁を作ります。
どちらも重要です。
主人公が柔軟なら、周囲の人物に頑固さを与えて対比させると効果的です。
また、思考の柔軟性はセリフにも反映されます。
相手の意見に耳を傾ける人なのか、遮って主張する人なのか。
会話のテンポが、その人の「頭の柔らかさ」を物語ります。
💡 ポイント
- 「予想外の出来事」にどう反応するかを決める
- 柔軟⇔頑固のバランスを登場人物同士で対比させる
- 柔軟さは強さ、頑固さは信念として描くと深みが出る
🧩 16|性格 ― 行動の“原動力”を一言で表す
Q:この人の「一番の口ぐせ」はなんでしょう?
性格は、キャラクターの動き出す理由です。
怒りっぽい、冷静、楽観的、神経質――
単語だけで並べるよりも、行動と口調で示すほうが印象に残ります。
たとえば、
・困っている人を見ると放っておけない(衝動的)
・人と話す前に必ず一拍おく(慎重)
・嫌なことがあっても笑ってごまかす(自己防衛)
性格とは、感情の癖であり、生き方の反射でもあります。
また、性格は「変化しないもの」ではありません。
物語を通して、性格の中の一部がゆっくりと変わっていく――
その揺れ幅こそがドラマの真髄です。
性格を設定するときは、「強さ」と「弱さ」の両面を入れてください。
強気な人は実は繊細、明るい人は孤独を抱えている。
矛盾を抱えた性格ほど、リアルで魅力的です。
💡 ポイント
- 性格を「動詞」で表す(例:信じる/疑う/逃げる/挑む)
- 性格が行動にどう現れるかを一場面で想像する
- 性格の矛盾(強がり×優しさなど)を1つ入れる
人物の性格を表すには、脚本のセリフを輝かせる7つのコツも参考になります。言葉づかいの癖やテンポがキャラ像をより鮮明にします。
🧩 17|他人との関わり方 ― “距離の取り方”が人間性を語る
Q:この人は、誰かと一緒にいるとき、沈黙を怖がりますか?
他人との関わり方は、キャラクターの「社会での呼吸」です。
人と深く関わるタイプか、距離を置いて観察するタイプか。
その姿勢ひとつで、作品全体のトーンが変わります。
たとえば──
積極的に助けようとする人は、他者の痛みに敏感な人。
逆に、関わりを避ける人は、過去の傷を抱えている人。
誰かとの距離を測るとき、キャラクターの過去がにじむのです。
また、人間関係の変化はドラマを作ります。
他人を信用しなかった人が、ある瞬間に心を開く。
あるいは、誰にでも優しかった人が、ひとりだけ拒絶する。
その「距離の伸び縮み」こそが、キャラクターを立体的に見せます。
💡 ポイント
- 他人との距離感を「近い/遠い/曖昧」で分類する
- 関わり方を変えたきっかけを一つ設定する
- 距離感の変化が、物語の成長や転機につながるようにする
🧩 18|他者からの印象 ― “見られ方”が生むギャップのドラマ
Q:この人は、周りからどう思われているでしょうか?
他者からの印象は、キャラクターの外側の顔です。
人は自分のことを正確には見られません。
だからこそ、他人の目にどう映るかを設定すると、人物像に立体感が出ます。
たとえば──
冷たそうに見える人が、実は誰よりも情に厚い。
明るく人気者の人が、孤独を隠して笑っている。
印象と本質の間にギャップがあるほど、読者は「知りたい」と感じます。
また、印象は相手によっても変わります。
上司からは真面目、友人からは面白い、家族からは頼りない――
どの目線から語るかで、キャラクターは別人のように見えるのです。
この項目では、「他人の語るキャラ像」を一行書いてみてください。
誰かの口から語られるキャラは、自己紹介よりも強い説得力を持ちます。
💡 ポイント
- 他人から見た「第一印象」と「本当の姿」の差を設定する
- 見られ方が変わるきっかけ(事件・失敗・告白など)を考える
- 第三者の視点でキャラを描写するセリフを一行入れる
🧩 19|脚本の途中で芽生える特徴 ― “変化”こそキャラクターの生命線
Q:物語が進むうちに、この人の中に何が芽生えますか?
キャラクターは、最初から完成されている必要はありません。
むしろ、変化していくことこそが、観客や読者を惹きつけます。
冷めた人が情熱を知り、臆病な人が一歩を踏み出し、
強がりな人が涙を見せる――。
その変化の芽がストーリーの中心に咲くのです。
ここで大切なのは、劇的な変化ではなく、小さなきっかけです。
誰かの一言、失敗、喪失、出会い。
たった一つの出来事で、キャラクターの考え方が少しだけ揺れる。
その「心の揺れ」を丁寧に描くと、読者は成長を感じ取ります。
また、変化は必ずしも良い方向でなくても構いません。
優しかった人が冷たくなる。
正義感の強い人が、自分の信念を疑い始める。
闇に沈む変化もまた、人間のリアリティです。
💡 ポイント
- 物語の前半と後半で何が変わったかを一行で書く
- 変化のきっかけを具体的な出来事として設定する
- 成長・堕落・覚醒など、どの方向の変化かを明確にする
🧩 20|野心(目標) ― 物語を動かす“エンジン”
Q:この人は、最終的に何を手に入れたいのでしょうか?
野心や目標は、キャラクターを動かす燃料です。
どんな作品でも、登場人物が何かを望んでいる限り、物語は前へ進みます。
それが小さな願いでも、大きな夢でも構いません。
重要なのは、「なぜそれを求めるのか」という動機の深さです。
たとえば──
成功して家族を安心させたい。
誰かに認められたい。
世界を変えたい。
欲望や夢の裏側には、たいてい過去の傷があります。
そこを掘り下げることで、単なる目標が生きる理由に変わります。
また、野心は物語の展開とともに姿を変えます。
最初は「お金」だった目的が、最後には「人を守ること」になるように。
変化する目標は、キャラクターの成長そのものを示します。
💡 ポイント
- 「何を」ではなく「なぜ」を掘り下げる
- 目標が叶った後に空虚さが残る構造も面白い
- 小さな目標(短期)と大きな目標(人生単位)を分けて設定する
キャラクターの目標設定を深めたら、三幕構成の作り方|物語を動かす骨格とはをチェック。目標とストーリー構成をつなげると、作品に一貫性が生まれます。
🧩 21|そのキャラクターの重要ポイント ― “一言で語れる人物像”をつくる
Q:この人を一言で説明すると、どんな人ですか?
キャラクターの魅力は、複雑でありながらも一言で言い表せることにあります。
それは肩書きでも属性でもなく、物語の中でその人が体現している本質です。
たとえば──
「誰よりも不器用な正義漢」
「優しさで自分を傷つける人」
「愛を知らないまま世界を救う少女」
このような一文があれば、読者や観客はすぐに興味を持ちます。
重要なのは、「他の誰でもなく、この人物でなければならない理由」。
同じ状況に置かれたとき、他のキャラとは違う選択をする――
その選び方こそが個性であり、物語を支える芯になります。
この項では、少し詩的でもかまいません。
「〇〇な××」という形で一言キャッチを作ってみてください。
それが、キャラクターのポスターコピーにもなります。
💡 ポイント
- 「〇〇な××」の形で一言キャッチを作る
- 行動・信念・弱点のいずれかを入れる
- その一言を物語のラストで裏切ると強烈な印象が残る
🧩 22|敵か味方か ― “立場”がキャラクターを際立たせる
Q:この人は、誰のために戦い、誰に逆らうのでしょうか?
物語の中で、キャラクターは必ず誰かの敵か誰かの味方になります。
それは戦いの構図だけでなく、価値観の対立でもあります。
つまり、何を守り、何に反発するかを決めることで、その人の信念が見えてくるのです。
たとえば──
理不尽な社会に反抗する主人公。
権力に従うことで家族を守る脇役。
正義を掲げながらも、主人公と対立する友人。
立場の違いが、キャラクター同士のドラマを生みます。
「敵=悪」ではなく、「敵=異なる正義」として描くと深みが出ます。
誰もが自分の正しさを信じて行動している――その構造こそ、リアリティの源です。
キャラクターの味方・敵の線をはっきり描くことで、物語全体が引き締まります。
💡 ポイント
- 「誰の味方で、誰の敵か」を一行で明確にする
- 敵対の理由を価値観の違いとして設定する
- 終盤で立場が逆転する展開を用意すると印象的
🧒 子供キャラクター設定の作り方 ― “未完成さ”をどう描くか
Q:この子は、どんな世界を見て、何をまだ知らないのでしょうか?
子供キャラクターを描くときに大切なのは、“欠けている部分”の魅力です。
経験や知識が足りないからこそ、世界をまっすぐに見ることができます。
その未完成さが、物語に新しい視点と感情の温度をもたらします。
大人キャラと同じ22項目を使って構いませんが、
いくつかの項目を「子供の目線」に置き換えると自然になります。
🧩 置き換え・追加のポイント
- 10. 仕事 → 学校・部活・得意教科
どんな教科が得意か、どんな友達と過ごしているか。
学校という小さな社会の中での立場を設定しましょう。
例:クラスで浮いている/リーダー的存在/先生に甘えられないタイプ - 06. 家族構成 → 家族との関係をより重視
年齢が低いほど、家族の影響が強くなります。
誰に甘え、誰を避け、誰に憧れているか――
それがそのまま性格の原型になります。 - 07. 友達との関係 → スクールカーストや距離感を意識
親友・いじめ・初恋など、学校内の関係性はドラマの宝庫です。
「誰といると安心するか」「誰の前では強がるか」を決めておくと立体的。 - 12. 趣味 → 好きな遊びや夢中になっていること
虫集め、ゲーム、空想――どんな小さなことでもOK。
子供の夢中は、そのまま個性として輝きます。 - 20. 野心(目標) → 「なりたい自分」
将来の夢や、小さな願い。
「ヒーローになりたい」「大人になりたくない」など、
その子の未来への姿勢を一言で書きましょう。
💡 子供キャラを描くコツ
- 大人の言葉を使わせすぎない(語彙より感情で動く)
- 知らないことを怖がるか、面白がるかを設定する
- 子供が発する一言が、大人を動かす構図を意識する
子供キャラクターは、物語の中で純粋さ・変化・希望を象徴します。
その存在が、大人キャラの価値観を揺さぶる瞬間を描けたとき、
作品に世代を超えた温度が生まれるでしょう。
🧭 まとめ ― キャラクターは“設定”ではなく“呼吸する存在”
キャラクター設定の22項目をすべて埋めても、それだけで「人間」が完成するわけではありません。
けれど、ひとつひとつの質問に向き合うことで、
あなたの中にその人が勝手に動き出す瞬間が訪れるはずです。
キャラクターは、整った設定よりも矛盾と揺れを持っているほうが魅力的です。
完璧さではなく、「それでも生きようとする不器用さ」。
そこに読者は共感し、作品世界の中で呼吸を感じます。
設定とは、息を吹き込むための地図です。
あなたが描く一人ひとりが、自分の言葉で話し、
自分の選んだ道を歩き出したとき――
その物語は、もう作者のものではなく、彼らの物語になります。
📥 テンプレート配布
この記事の22項目をそのまま書き込める【キャラ設定テンプレート】を無料配布中!
Word版を用意しています。
あなたの物語づくりに、ぜひご活用ください。
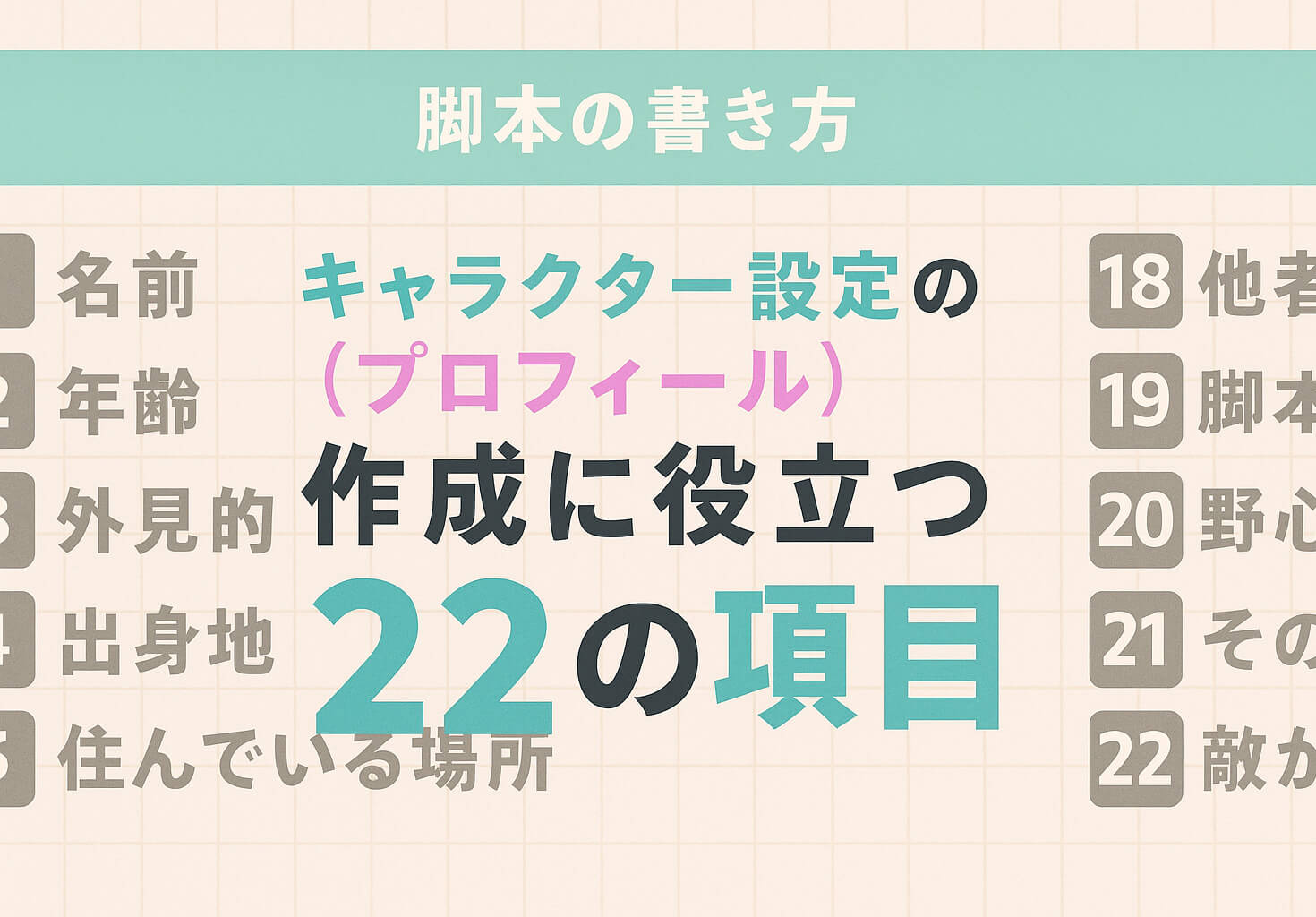
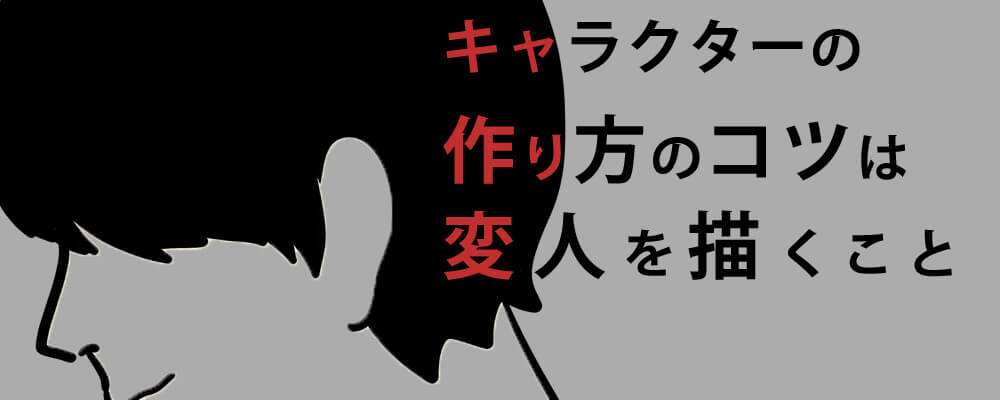

コメント