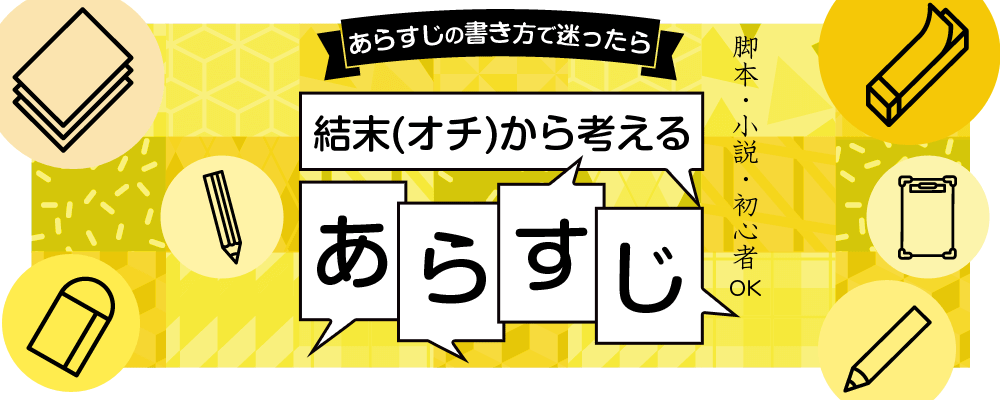
あらすじの書き方で迷ったら結末(オチ)から考える![脚本/小説/初心者OK]
この記事は 2023年10月24日 に更新されました。
あらすじは、脚本や小説の本文を要約した文章です。脚本や小説、Amazon商品ページやウィキペディア、読書感想文など、メディア(媒体)によってあらすじの書き方は異なります。このような書き方の違いが、あらすじの理解を難しくしてきました。しかし、どんなメディアにも対応可能なあらすじの書き方は存在します。記事では、あらすじを迷わずに書くための考え方や手順について解説します。
目次
結末(オチ)から考えるあらすじの書き方1:
前提条件

あらすじの書き方を身につけるには前提条件があるよ
あらすじは、本文を要約する文章です。そのため、物語が完結していなければあらすじは書けません。この前提は、あらすじを書くための必須条件です。
また「脚本や小説を書き出す前のラフスケッチ」としてあらすじを書く人がいますが、認識が誤っていると言わざるを得ません。なぜなら、ラフスケッチに該当する資料はプロットのことであり、その役目を担うのはあらすじではないからです。プロットは作者の執筆を補佐するための資料ですが、あらすじは読者を本文に引き込むための文章です。


2020.04.24
プロットとは? 基礎知識と書き方のコツ
プロットはシナリオを書き出す前の下準備。プロだっておろそかにしない大切な工程です。 プロットの書き方については、脚本家の間でも解釈が異なります。初心者には更に難解でしょう。 だからといって、プロットを省いて、いきなりシナリオを書き出すとかえって大変な思いをするかもしれません。 確...
- あらすじは物語が完結していないと書けない
結末(オチ)から考えるあらすじの書き方2:
手順
あらすじの書き方は、決められた手順に従うと簡単です。
あらすじの書き方の手順
- 結末(オチ)からさかのぼってエピソードを並べる
- 時系列に沿ってあらすじを書く
昔話『桃太郎』を例に詳しく解説します。
手順1にある「結末(オチ)」は、「桃太郎は村に宝を持ち帰った」というエピソードのことです。「鬼との戦い」はクライマックスであり、結末ではないので注意してください。結末とは、色々あって結局こうなったという状態のことです。そして「結末(オチ)」は、あらすじを考えるスタートラインでもあります。
手順2では、結末からエピソードをさかのぼります。各エピソードは因果関係で繋がっていなければいけません。その際、「なぜ」「どうやって」と自問すると考えやすいです。
たとえば「桃太郎は村に宝を持ち帰った」というエピソードに対して、「どうやって?」と自問すると、「桃太郎が鬼を退治したから」という答えが導き出せます。これが次のエピソードとしてつながるのです。
この作業を繰り返して、冒頭エピソードまでたどり着けばOKです。その際、因果関係でつながらないエピソードがあれば、ストーリーが破綻していると考えられます。
桃太郎のエピソードを結末から並べた例
- 桃太郎が、村に宝を持ち帰った(どうやって?↓)
- 桃太郎が、鬼を退治したから(どうやって?↓)
- 桃太郎は、犬猿雉に協力してもらったから(どうやって?↓)
- 桃太郎は、きびだんごで犬猿雉を仲間にしたから(どうやって?↓)
- 桃太郎は、おばあさんからきびだんごを貰ったから(なぜ?↓)
- 桃太郎は、鬼退治に行くと決意したから(なぜ?↓)
- 桃太郎は、村の平和を守りたかったから(なぜ?↓)
- 桃太郎は、村に住むおじいさんとおばあさんに大切に育てられたから(なぜ?↓)
- 桃に入った桃太郎が、おじいさんとおばあさんに拾われたから




エピソードを書き出だすと物語を整理できるよ
次に、書き出したエピソードを時系列に沿って並べ直してください。たったこれだけで、様々なメディアに通用するあらすじが書けます。
桃太郎のあらすじ例
桃から生まれた桃太郎はおじいさんとおばあさんに大切に育てられました。村は鬼の脅威にさらされていました。そこで村の平和を守りたい桃太郎は鬼退治に出かける決意を固めます。おばあさんから貰ったきびだんごで犬猿雉を仲間に入れた桃太郎は、力を合わせて凶暴な鬼に立ち向かいます。やっとの思いで鬼をやっつけた桃太郎は宝を村に持ち帰りました。(156文字)
ちなみに、あらすじの文字数はメディアによって異なります。文庫小説のあらすじ文字数は170~200文字程度、映画DVDパッケージのあらすじは300~150文字程度です。一方、多くの脚本コンクールでは「800文字程度であらすじを書く」と規定で決まっています。
- あらすじは結末(オチ)から逆順に考える
- なぜ?どうやって?でエピソードがつながるように意識する
オチまで書くべきか
あらすじでオチを書くべきかどうか、悩む人は多いでしょう。これもケースバイケースです。
例えば、販売目的の小説やAmazonの商品紹介ページに掲載するあらすじの場合、購入を促すためオチを書きません。
一方、シナリオコンクールや小説公募に応募する場合、あらすじにはオチまで書きます。あらすじのオチを隠すと、審査員を馬鹿にしているという誤解が生じかねません。即落選する危険が生じるので最後まで書いてください。
インターネットでは、読者に配慮してオチを書かない風潮があります。その一方「ネタバレあり」と注意喚起をしてからオチまで書くブログや、オチまで書くように推奨するウィキペディアのようなメディアも少なくありません。
学校課題の読書感想文は、必要に応じてオチを書き分けます。しかし、決まったルールはないので、都度確認すると安心です。
結末(オチ)の有り無しに関わらず、上記で紹介した「結末から考えるあらすじの書き方」は活用できるでしょう。あらすじを全て書き終えた後、オチが不要なら削ればいいだけです。
結末(オチ)から考えるあらすじの書き方3:
メリット
結末から考えるあらすじの書き方には3つのメリットがあります。まず1つ目は一貫性を生むこと。2つ目は読みやすいこと。最後は客観性を持てることです。
メリット1_一貫性を生む
苦労して書き上げた脚本は我が子も同然。しかし、その魅力を一つ残らず伝えようとするあまり、あらすじが長文になりすぎてはいけません。あらすじに限らず、文章は長くなるほどメインテーマからそれる傾向があるからです。
あらすじは、メインテーマに絞り、一貫性を持って伝えるようにしましょう。
結末から考えるあらすじの書き方を実践すると、テーマに一貫性を持つエピソードのつながりができます。それは最も魅力的なエピソードです。
それが伝われば、読者は他のエピソードにも興味を示します。すなわち、本文を読みたくなるのです。あらすじの役割は本文を読ませること、ということを忘れてはいけません。
また、あらすじに一貫性があれば、自然と主人公にスポットが当たります。主人公がどういう人物か明確になれば、多くの読者が物語にも興味を持つでしょう。
- あらすじは、メインテーマに絞り一貫性を持って書く
メリット2_読みやすい
脚本や小説の本文は、面白さを追求する過程で、構成を複雑にしたり、伏線を張ったり、秘密を作ったりして工夫します。どれほどシンプルなストーリーでも、文章に演出の跡は残るものです。
しかし、あらすじでは、このような演出は必要ありません。文字数が限られた中で試行錯誤しても、読みにくくなるだけです。あらすじが読みにくいと、本編は見向きもされないでしょう。あらすじの文章は、読みやすくなければいけないのです。
読みやすい文章とは、エピソードが時系列に並んでいます。冒頭で天地人(いつ、どこで、だれが)を明らかにすれば、さらに読みやすくなるでしょう。今回紹介したあらすじの書き方を実践していただければ、自然とエピソードが時系列に揃います。読みやすいあらすじが、簡単に書けるはずです。
- あらすじは読みやすさ重視!無駄な演出不要
メリット3_客観性を持てる
脚本家や小説家の中には、登場人物になりきって主観的に執筆する人がいます。大切な資質ですがそれだけでは足りません。同時に客観性も併せ持たなければ、強固なストーリー構造は確立できないでしょう。主観と客観という2つの視点をバランス良く持つことは、優れた作品を生み出す絶対条件です。
しかし、言うは易く行うは難しです。2つの視点を併せ持つことは難しく、多くの見習い作家が主観に偏って執筆しがちです。そのため、物語に破綻があっても、気が付きません。
ある脚本家は、2~3日の冷却期間を経てから自作を俯瞰することで客観的な視点を手に入れると言います。しかし、時間的な余裕がなかったり、自制心が弱かったりする場合は難しいでしょう。
そんななか、結末からあらすじを考える作業は、主観を客観に切り替えるきっかけとなります。通常、あらすじは冒頭から順に追うものであり、結末からさかのぼって考えません。ある種の異常な作業だといえます。さらに、この作業はロジカルに考える必要があるため、客観性を取り戻せるのです。




客観的な視点を持つと、破綻した箇所はもちろん、掘り下げて書くべきポイントも明確になるよ。その気付きは、そのままリライトポイントに置き換えられるんだ
- 客観的な視点が自然と手に入る
- 新たな気付きはリライトポイントに置き換えられる
まとめ
あらすじの書き方で迷う人は、まず結末(オチ)を書いてください。そこからさかのぼってエピソードを書き出した後、改めて冒頭から書き直します。すると、メインテーマを中心に据えた一貫性のある文章が書けるはずです。時系列に整った読みやすい文章が書き上がります。さらに思考順序を通常と逆にしたことで客観性が生まれ、自作を冷静に見直すきっかけにもなるでしょう。その際、発見した破綻箇所や改善点はリライトの道標となるはずです。
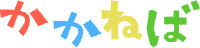
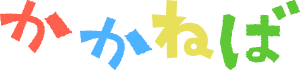


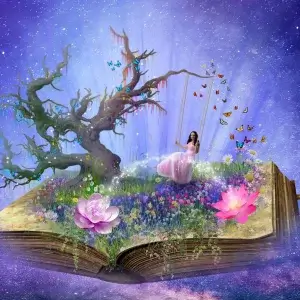
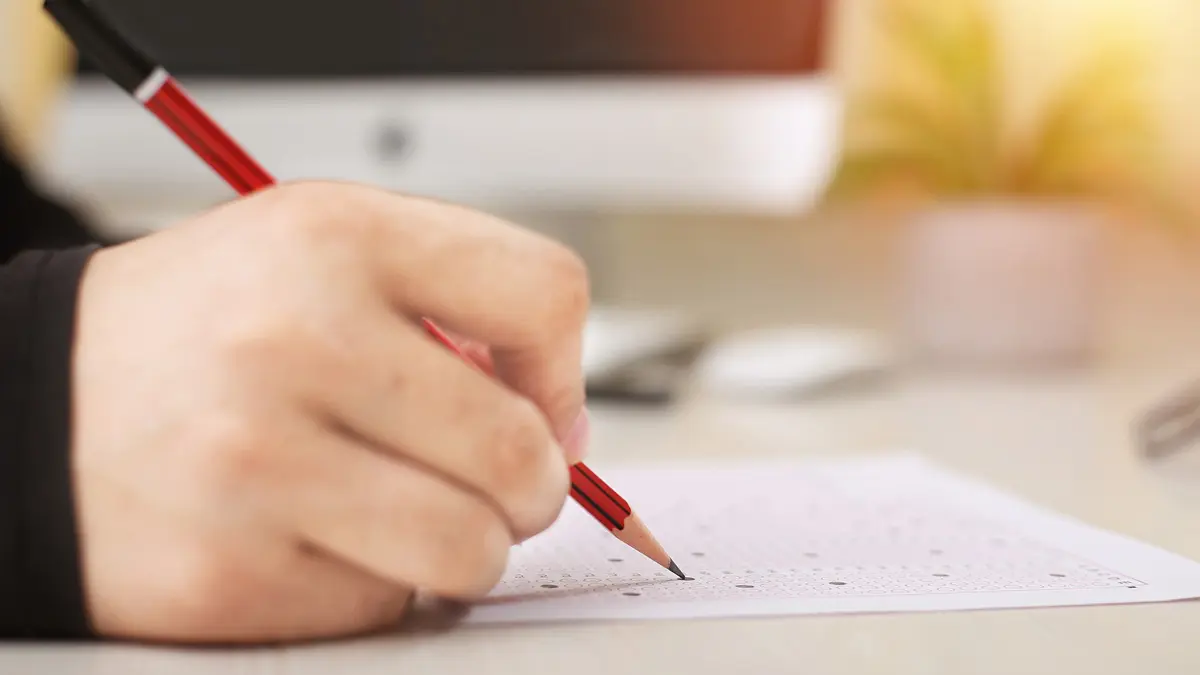

この記事へのコメントはありません。