
脚色とは? その意味や脚本との違いについて
この記事は 2023年6月20日 に更新されました。
脚色(きゃくしょく)は、映画や演劇などにおいて、原作や実際の出来事を元に創作活動を行うことです。実際、世の中にはたくさんの脚色作品が存在します。しかし、その意味や役割、似ている言葉の脚本との違いなどについて理解している人は多くありません。記事では、脚色について解説します。
目次
脚色とは
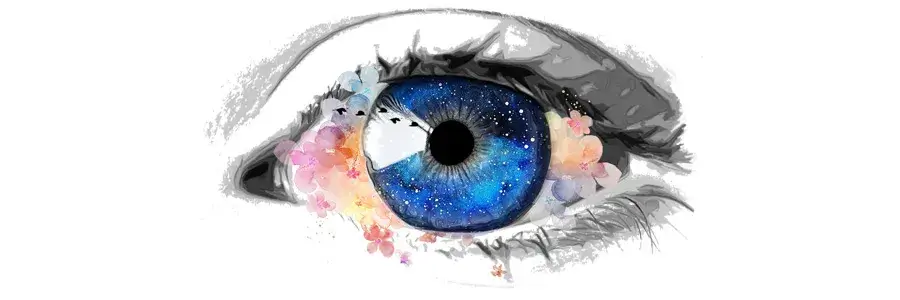
脚色(きゃくしょく)とは、物語や出来事を創作する際に、原作や実際の事実を一部改変して表現する創作方法です。
脚色は、文学作品や映画、演劇などの世界で頻繁に使われてきた言葉です。例えば、小説や漫画などといった原作のストーリーやキャラクターを映像化に適した形にアレンジしたり、歴史上の出来事や事件をフィクションに織り交ぜたりします。
ただし、これら原作や実際の事実との間に一定の齟齬が生じる点には注意が必要です。脚色を行う場合は、原作や実際の事実との違いを認識しなければなりません。
脚色の語源

脚色の語源は、漢字の「脚」(きゃく)と「色」(しょく)から成り立ちます。
「脚」は、本来は「足」を意味する漢字です。物事の基盤や基礎部分を指します。一方の「色」は、本来は「色彩」や「外見」を指す漢字です。転じて「要素」や「特徴」という意味でも用いられます。
脚色は、演劇や文学の世界で使われていた言葉です。舞台の設定や演技の方法を示すことを脚色と呼んでいました。脚色を加えることで、作品の効果や魅力を高めたのです。
現代では、原作や実話を元にして創作改変や変更を表す言葉として、脚色という言葉が使われています。
脚色の歴史

脚色の歴史は、文学や演劇の起源と深く関連しています。古代ギリシャの劇作家たちは、神話や伝説を題材にした作品を創作し、その際に脚色が行われていました。彼らは原作を基にして物語を構築し、演劇の効果や観客の感情を引き立たせるために自由な改変やアレンジを加えたのです。
また、中世ヨーロッパの劇作家たちも、聖書や伝説などの物語を演劇化する際に脚色を行っていました。彼らは原作の内容やキリスト教の教義に忠実である一方で、劇的な状況や登場人物の心情をよりドラマティックに表現するために変更を加えています。
日本では、江戸時代になってから歌舞伎の仕組みとして作品に脚色が使われていました。1830年~1844年ごろには、江戸で読本や講談などに脚色が用いられていたようです。その後は、新聞に連載している評判小説の劇化にも脚色するようになったようです。
近代以降、文学や演劇の世界ではさまざまな脚色が行われてきました。文学作品の映画化や舞台化では、原作をより視覚的な表現に適した形に変えるために脚色が行われています。また、歴史上の出来事を題材にした作品では、事実と創作が織り交ざった脚色が行われてきました。
脚色と脚本の違い

脚色(きゃくしょく)と脚本(きゃくほん)は、異なる役割を持つ概念です。
脚色は、原作や実際の出来事を一部改変し、創作の自由や効果を追求する行為そのものを指します。脚色は、物語の魅力や効果を高めるために行われる行為です。
一方、脚本は作品の台本としての役割を持つ文書のことです。演劇や映画、テレビドラマなどの制作過程で使用され、登場人物の動きやセリフ、舞台の設定や効果など、具体的な表現方法を書きます。制作者にとっては創作活動の指針です。
簡単に言えば、脚色は原作や実際の出来事を改変して行う創作行為であり、脚本は作品の具体的な台本や演出を書いた文章です。
脚色の魅力

脚色(きゃくしょく)には、いくつかの魅力があります。
- オリジナリティと自由が増す
原作や実際の出来事をベースにしつつ、脚本家のアイデアや解釈を加えられます。新たな展開や作品の隠れた魅力を発掘することができるでしょう。 - 映像的なストーリーに最適化
脚色は、映像的なストーリーに最適化する手段です。原作や実際の出来事を忠実に再現するだけではなく、映像化した際のストーリーのテンポや構造を調整したり、登場人物の心情や設定にスポットを当てたりして、観客により強い感情や共感を呼び起こすことができます。 - 新たな魅力の発見
脚色によって、物語や登場人物に新たな視点や解釈が加えられます。原作や実際の出来事とは異なる角度からのアプローチや深い洞察が可能です。それらが作品に新たな魅力を付加することに繋がります。また、過去の作品であっても、切り口を変化させることで、今の時代や文化にマッチした現代的な意味を持つこともあるでしょう。
脚色の成功例

脚色は多くの映画で用いられている手法であり成功例も数多く存在します。以下にいくつかの脚色の成功例を示します。
映画『ロード・オブ・ザ・リング』(原作者:J・R・R・トールキン)
原作の大作ファンタジー小説を映画化する際に、監督のピーター・ジャクソンが脚色を作りました。この脚色により、視覚的なファンタジーの世界観が実現され映画は大ヒットしました。
映画『シンドラーのリスト』(原作者:トーマス・キニーリー)
実際の出来事を基にした映画であり、原作小説を脚色しました。 監督のスティーブン・スピルバーグは物語の一部を変更し、登場人物の関係性やドラマティックなシーンをより強調しました。この脚色により、実在の人間ドラマがより深く描かれ、感動的な印象を考える作品となりました。
映画『エバーアフター』(原作:グリム童話)
グリム童話のシンデレラを脚色した映画です。主人公の少女はシンデレラではなくダニエルであり、舞台は16世紀のフランスに変更されています。ダニエルが、王子ヘンリーと出会って逆境にも負けず恋をしていく様子が表現された作品です。
映画では、主人公・ダニエルの無邪気な姿が、原作のシンデレラとは違うキャラクターである点も見所です。一方、王子とシンデレラの出会いや味方になる人物にも工夫が見られます。
映画『ソーシャル・ネットワーク』(原作者:ベン・メズリック)
映画監督のデヴィッド・フィンチャーは、フェイスブックの創始者マーク・ザッカーバーグの話を基にした映画を制作しました。その結果、社会的なテーマや人間ドラマにスポットが当てられ、多くの賞を受賞するなど高い評価を得ました。
映画『ショーシャンクの空に』(原作者:スティーブン・キング)
この映画は、スティーブン・キングの小説を原作としています。 原作では主人公の内面の描写や時間の経過が詳細に描かれていますが、映画では一部のエピソードやキャラクターを削除し、物語のテンポや流れを変更しています。これにより、映画は原作とは異なるアプローチでストーリーを展開し、広く称賛される成功作となりました。
映画『フォレスト・ガンプ/一期一会』(原作者:ウィンストン・グルーム)
この映画は、ウィンストン・グルームの著作を原作としています。ストーリーを語る視点に工夫が見られており、キャラクターやエピソードに映画オリジナルのアレンジが加えられました。映画は感動的なストーリーとトム・ハンクスの演技によって大成功を収め、アカデミー賞など多くの賞を獲得しました。
脚色から新たな物語を感じる
原作を観て飽きてしまった作品でも、脚色をした作品に出会うことで、それまでと違った面白さを発見することができます。脚色をすることは、オリジナル作品に無限の可能性を見ることです。脚色がうまくいきさえすれば、一つの作品からあらゆる魅力を掘り起こせます。
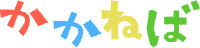
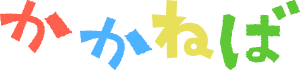
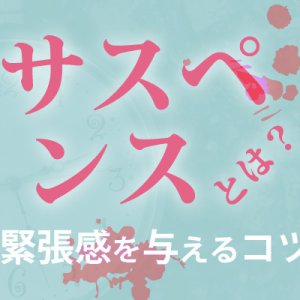


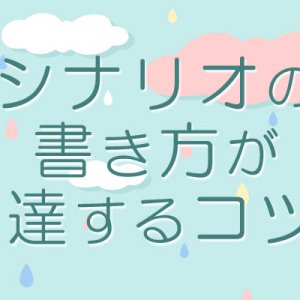
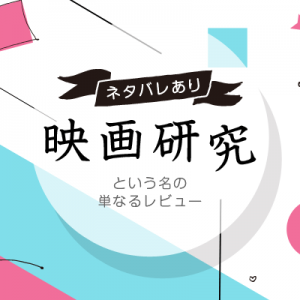
この記事へのコメントはありません。